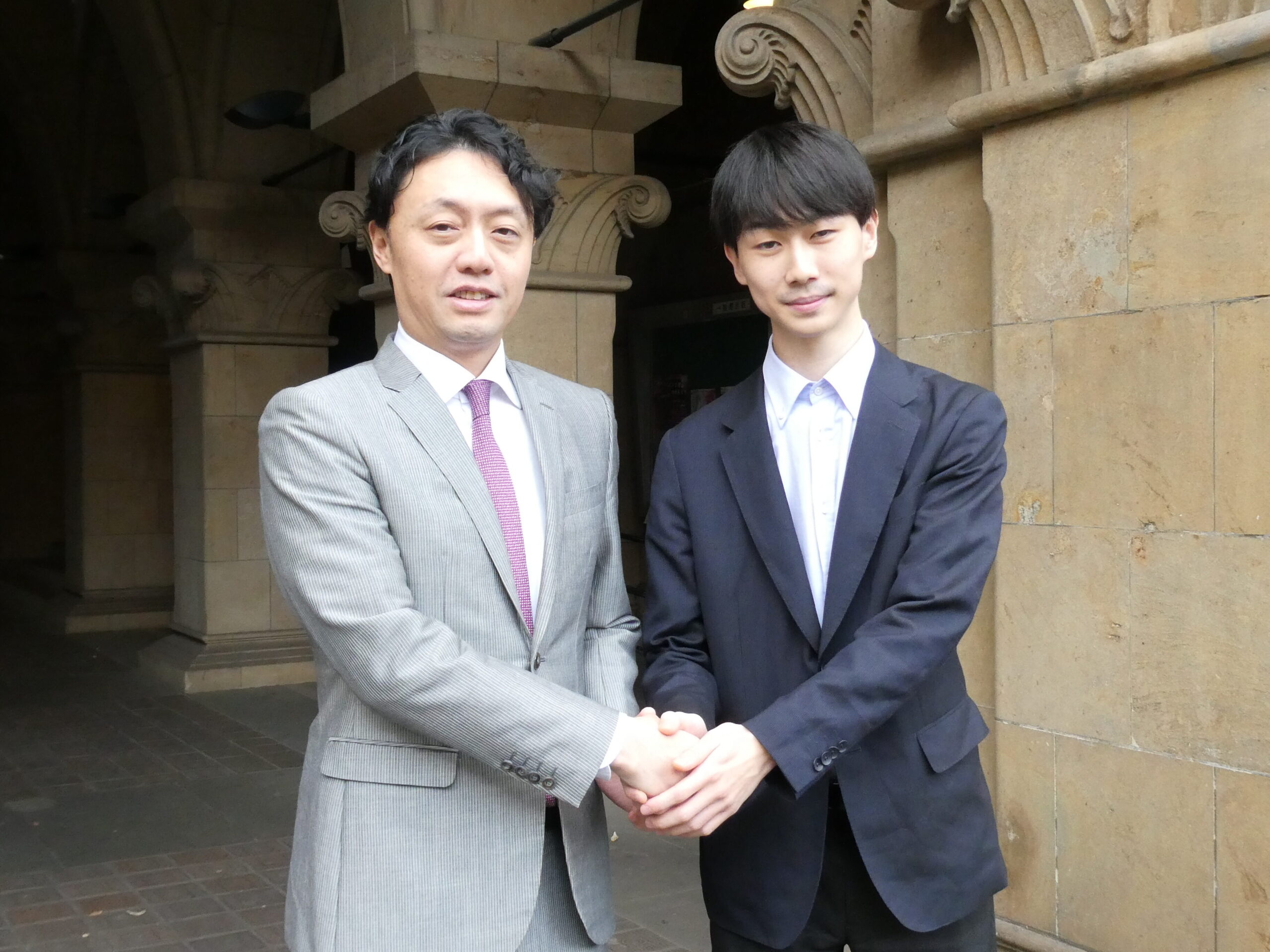東京大学大学院工学系研究科 松尾・岩澤研究室(以下、「松尾研」)は、松尾豊が理事を務める一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)と連携し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「AIを用いた汎用ロボット開発加速に向けた学習向けのロボット動作データセットの構築およびロボット基盤モデルへの応用可能性への検証についての調査」において、ロボティクス領域における基盤モデルの開発と大規模なデータ収集を開始しました。数万時間のデータ収集を目標としロボットAIモデルの構築を目指すとともに、研究者・エンジニアとの協働を通じた技術開発体制を強化してまいります。
■ 背景
近年、大規模言語モデル(LLM)や視覚言語モデル(VLM)の飛躍的な進化とロボティクス領域への応用により、ロボットがより汎用的なタスクに柔軟に対応できる可能性が拓かれてきています。π0(Physical Intelligence)やGR00T(NVIDIA)といった先行事例に見られるように、マルチモーダルな大規模モデルを応用したロボティクスの取り組みは、今後のロボティクス領域の技術基盤として重要な位置を占めていくと考えられています。
こうした背景のもと、ロボットが実環境で多様なスキルを獲得し、継続的に学習・改善を重ねられるような、汎用性のある基盤モデルの構築や大規模なデータ収集は国際的に重要な研究テーマとなっています。
■ 取り組み内容
松尾・岩澤研究室は、本取り組みにおいてAIRoAと連携し以下のような活動を推進します。
これらの取り組みを推進し、将来的には、現場環境での検証・PoCを通じて、AIロボットによる小売・製造・物流などの分野での社会実装も目指します。
- ロボット基盤モデルの開発
ロボットが人間と同等の文脈理解力を持ち、未知の環境でも柔軟に行動できるよう、大規模マルチモーダルデータを用いた学習済みモデルの構築を行います。多様なロボットやセンサー情報に対応可能な汎用性と、現場ニーズへの適応性を両立する設計が特長です。 - 数万時間規模のロボット稼働データの構築支援
日本・海外拠点での大規模なロボット運用から得られるデータの整備にも、アーキテクチャ設計や評価指標策定の面で主体的に関与。モデル学習に適した高品質・高密度なデータセットの開発を加速させます。 - ロボット基盤コンティション運営による人材育成
松尾研が開催する大規模言語モデル(LLM)などの講義や、産業界の技術者より関心のあるメンバーを集め、コンペティション形式で開発を実施することで、AIロボット人材の育成を目指します。
■ 東京大学 松尾・岩澤研究室 ロボティクス研究ユニットについて
松尾・岩澤研究室では、実世界と相互作用する実機を通じて「知能とは何か」を解き明かすことを目指し、ロボティクス研究を積極的に推進しています。
研究室には、ロボットアームやモバイルマニピュレータといった実機に加え、各種シミュレータ、VRデバイス、マルチモーダルセンサなど多様なハードウェア環境を整備し、仮想環境から実環境に至るまで幅広い検証が可能な研究インフラを構築しています。
研究開発コミュニティとしては、学内外の学生・研究者が参加する「TRAIL(Tokyo Robotics and AI Lab)」も運用し、現在では50名規模にまで拡大。ロボカップでは国内大会・世界大会共に上位入賞を果たすなど、実践的な技術力とチーム力を備えた研究体制を形成しています。
また、2025年4月より、AIとロボティクスの融合を体系的に学ぶ教育講座Physical AI講座も開講し、次世代の研究者育成と応用研究の加速にも力を入れています。これまでの研究成果はICRAをはじめとするトップ国際会議に採録されており、基礎から応用に至るまで幅広い領域で成果をあげています。
本プロジェクトでは、これまで当研究室が蓄積してきた大規模モデル開発やアプリケーション開発のノウハウを活かし、ロボティクス基盤モデルの開発拠点として中心的な役割を担います。
■ 今後について
本取り組みは、AI技術の最先端研究とロボティクスの現場知見を融合し、日本の産業におけるAIロボット導入を目指すものです。松尾・岩澤研究室では共にロボティクス研究を推進するリサーチャー・リサーチエンジニアを積極的に募集しています。詳細は下記求人をご覧ください。https://herp.careers/v1/weblab/crh6BsRjCxX1